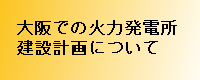陽電子をプロープとする有機ケイ素高分子の内部構造解析
化学部会(2008年4月度)研修会報告
日 時 : 2008年4月17日(木)
テーマ :講演会と年次総会
講演 陽電子をプロープとする有機ケイ素高分子の内部構造解析
堂丸 隆祥 工学博士 大阪府立大学名誉教授 株式会社FUDAI 学術顧問
はじめに
ケイ素ラジカル(・SiCl3)の反応速度論、シラン(SiH4)の赤外多分子分解、有機ポリシランの導電特性など、主にケイ素化学の分野の研究を行ってきた。本日は、陽電子消滅寿命法による、高分子内部の非破壊構造解析について紹介する。
陽電子消滅寿命法による内部構造の解析
陽電子は電子の反粒子であり電子と衝突すると、γ線を180度の方向に2本放出し自身は消滅する。なお、陽電子の線源は22Naを利用した。
陽電子消滅寿命法による分析の原理を図1で説明する。発射された陽電子は結晶格子を通過する間に熱化し、格子欠陥や空孔があればそこにトラップされる。トラップされた陽電子は周辺の電子と対になって、positronium(電子と陽電子が相互に相手を中心として回転)を形成し、消滅する際にγ線を放出する。陽電子発生の際のγ線と、消滅の際のγ線の時間差を測定すれば、格子欠陥(空孔)の大きさの測定や、高分子鎖間の自由体積(図3参照)の測定が可能となる。
陽電子の寿命を測定する装置の概略を図2に示す。対となったγ線カウンターの間に、セルとして純鉄を使用してサンプルと線源を挟む方式であり、サンプルを入れた時と入れない時の陽電子の寿命スペクトルを測定する。なお、純鉄を使用するのは格子欠陥が少ない材料であることによっている。
図1
図2 陽電子寿命測定装置概略
化学への応用
図3に高分子鎖間の自由体積の模式図を示す。自由体積は、高分子の粘弾性・ガラス転移・気体の拡散・誘電性などと密接に関係する重要なパラメータであるが、陽電子消滅法ではこの自由体積を直接測定することができる。測定自由体積とBondi法で計算した自由体積との間には強い相関関係が見いだされた。また、自由体積の逆数と酸素透過係数の間には良好な直線関係が得られた(図4)。
このように原子に占有されていない空間を非破壊的に測定することが可能であるため、今後の活用を期待したい。
図4 自由体積の逆数と酸素透過係数
有機ポリシランと陽電子消滅寿命法
有機ポリシランは、ケイ素を主鎖骨格とする高分子である。炭素骨格高分子との相違点は、図5に示すようにケイ素の持つσ共役に起因して主鎖上に電子が広がることにある(電子の広がりをドメインと呼ぶ)。このことにより有機ポリシランは特異な光電特性を持つ。即ち、UV領域での吸収・発光や、高い正孔移動度を持つため、フォトレジスト・電子写真感光体、有機EL素子などへの応用が期待されている。
陽電子消滅寿命法を用いて、ケイ素主鎖間の距離を測定することにより、正孔移動特性の中でこれまで見過ごされてきた部分に新しい光を当てることができ「新しいモデル」を構築することに成功した。
結論として陽電子消滅寿命法は内部自由体積を非破壊で測定する有力な方法といえるのでご活用願いたい。
図5 ポリシランのσ共役
図6 電界と正孔ホッピング
大阪府立大学と、大学発ベンチャー「株式会社FUDAI」の紹介
大阪府立大学には放射線研究センターがあり、密封線源・電子線加速器・イオン加速器、密封放射線同位元素・分析計測装置を備えている。陽電子消滅寿命法による測定も可能である。外部からの利用も可能であるため、産学官連携など共同研究に使用されている。
産学官連携の新しい形として、教職員及び賛同者による出資を受けて「株式会社FUDAI」を平成16年6月に設立した。(株)FUDAIでは府大の産学官連携を支援するとともに、「ものづくり後継者育成特修塾」を開いている。特修塾は1年計画のスケジュールで毎年20人程度を対象に、大学教授や実業界専門家が講師となって、ものづくりの場での実践的なノウハウの取得や、グループ研究を行っており4期目に入っている。企業の後継者育成の場としてご活用願いたい。企業からの技術相談などにも、府大の先生方の指導を受けながらきめ細かく対応している。
Q&A
Q 陽電子消滅寿命法は、どの程度まで応用可能か。
A フィルムを非破壊で、空孔の密度や大きさ及びその中身まで覗ける。EPMAなどは電子線で削り取りながらの観察であるが、この方法は非破壊である。
Q ドメインについてもう少し詳しく伺いたい。
A ドメインとは電子雲の広がりと考えたらよい。芳香族環はπ電子が拡がっているので一種のドメインと言える。Siはσ電子が電子雲を作っているが、Cの1重結合は広がらないので電子雲を作らない。
Q 自由体積と誘電性との関連を教えて欲しい。
A 絶縁性と同義だが密と粗の具合であり、空孔の大きいものは電気が流れにくい。
Q 純鉄の格子欠陥が少ないのはなぜか。
A 鉄は全ての原子核の中で最も安定であることに起因しているかも知れない。
(図は講演資料から転載)
文責 藤橋雅尚