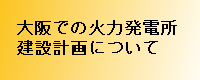「緑色蛍光蛋白質:GFPの化学」(ノーベル賞 化学賞)について
化学部会(2010年2月度)研修会報告
日 時 : 2010年2月18日(金)
テーマ : 講演会
講演 「緑色蛍光蛋白質:GFPの化学」について
黒田 誠 技術士(化学部門) 黒田技術士事務所代表
元 武田薬品工業株式会社、株式会社日立製作所
はじめに
下村修博士は2008年度のノーベル化学賞を受賞された。演者は大学で下村先生から直接実習指導を受け、米国招聘直前に結晶化に成功したルシフェリン(酵素によって酸化され発光する物質の総称)の青色発光を見せていただいた数少ない一人である。月刊技術士(2010年10月号)に「生物発光の化学」と題して投稿させていただいたが、本日は投稿の際、紙面の都合上報告しきれなかった内容を含めてお話しする。
同時受賞の3博士とその業績
2008年度のノーベル化学賞は、GFP(Green Fluorescent Protein)の発見からその活用で貢献した3人の博士の共同受賞である。
下村修博士 GFPの発見(1962)、発色団の解明と構造推定(1979)
R.Y.Tsien博士 遺伝子変異を導入する事で数々の蛍光蛋白質を開発(1992)
M.Chalfie博士 遺伝子組換により異種生物上でGFPを発現(1994)
この受賞は、GFPの発見(生物発光の基礎研究)→ 科学技術の進歩(分子生物学・遺伝子工学等の進歩)→ 医学・生命科学からの要請(バイオイメージング技術の進歩)の段階を踏み、集大成された業績として評価されたものと見なせる。
下村博士の業績
オワンクラゲの発光メカニズムは、イクオリンがCa+2により、蛋白質の構造が変形し、CO2を発生しながら青色に発光し、この青色の波長(エネルギー)によりGFPが励起され緑色の蛍光を発する事にある。
下村博士は1979年にGFPの発色団について、チロシン・セリン・グリシンの3つのアミノ酸が酸化、脱水縮合の結果できた図1の構造であり、図2のメカニズムで発光することを解明した。
図1
図2
R.Y.Tsien博士の業績
博士はランダムにGFP遺伝子に変異を起こさせ、緑色以外の色調を持つ2種類の蛍光蛋白質を単離し、解析してGFPの66番目のアミノ酸部分が他のアミノ酸に変わった蛋白質を発見。その他、六放サンゴからの赤色蛍光物質など多彩な色の蛍光蛋白質を発見し、目的とする蛋白質をカラフルにイメージングする技術を確立した。
M.Chalfie博士の業績
遺伝子組み換え技術を用いて、GFP遺伝子を目的とする蛋白質合成遺伝子にプロモータと組み合わせ導入し、線虫でGFPを発光させる事に成功したのが大きな業績である。この技術は生きたままの状態で観察する手法に発展し、今では医学、分子生物学、或いは医薬開発の有効な手段の基礎となっている。
GFP発見関連の話題
一般に海ホタル等の生物発光の仕組みは、図3の上部に示した「ルシフェリンとルシフェラーゼの反応」である。これに対し、オワンクラゲの例で提唱したのが図3の下部に示した「フォトプロテイン型の反応」である。即ち、オワンクラゲは発光システムと蛍光システムが共存している特異な生物と言える。
図3
下村博士に関するエピソードは多々ある。その一つは、プリンストン大学に招聘してくれた教授と研究方針で意見が衝突して、やむなく教授とは別々に実験台の片隅で実験するという気まずい雰囲気になった事件、さらにGFPの発色団の解明でもオワンクラゲ約85万匹から十数年かけて貯め続けた僅か100mgのGFPを用い、GFP発色団の推定並びにイクオリンとGFPの相互発光メカニズムの解明に至った研究成果と根気は驚嘆に値する。
常に問題意識を持った探求への姿勢とセレンディピティーがノーベル賞につながる研究になったと考える。
(講演終了後、GFPのサンプルと海ホタルの発光現象を見せていただいた)
Q&A
Q 一般に教授と軋轢があると研究を続けられないものだが、どのようにして解決されたのか。
A イクオリンの発光を抑制する要因がpHにあり(pH4)、Ca2+の影響でイクオリンが爆発的に発光する事を直ちに報告して人間関係を修復した。その後の研究論文も共同で発表し全面的な協力を得ている。
Q ルシフェリンの精製実験で学生、職員が先生の所に寄り付かなかったのは何故か。
A 実験は水素ガス気流中で裸のヒーターを使うなど、非常に危険と思い誰もが寄りつかなかったと述懐されている。
(図は講演資料から転載)
文責 藤橋雅尚 監修 黒田 誠