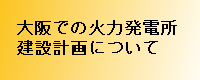創薬における 運・鈍・根
近畿本部 化学部会(2014年6月度) 講演会報告
日 時
: 2014年6月19日(木) 18:00~19:30
場 所 : K of Ks’
講演 : 創薬における運・鈍・根
浜理薬品工業株式会社 目黒 寛司(元武田薬品工業株式会社 取締役創薬研究本部長)
1.日本における創薬の歩み
創薬という言葉は1984年に作られた比較的新しい概念である。1970年代までは輸入、天然物、製法特許の潜りなど混沌としていたが、1976年に物質特許制度ができ模倣の時代(ミートゥー薬、ゾロ新薬)を経て、創薬による新薬黄金時代《格差拡大の時代(1990年代のブロックバスター薬など)、淘汰の時代(2000年代:独創性の勝負・M&A)》へ移っていった。しかし、2011年~2014年にかけて世界トップの10製品が全て特許切れとなり、2010年代はバイオ医薬品やジェネリック薬の時代に移っていくと感じている。
本日は恩師の竹本先生が提唱された、「運・鈍・根」の観点から創薬についてお話しする。
2.新薬の開発について
低分子の医薬品について現時点で考えて見ると、次の様な課題がある。
①既に多くの病気で良い薬が出尽くしている(Unmet Needsがほぼ満たされている)?
Unmet Needs:医薬品が医療ニーズを満たしていない状態
②新しい研究ターゲットが少なくなっている?(研究ターゲットと病態の関わりが課題)
③残っているUnmet Needsの高い医薬品は何か?
その中で、従前からの流れ(強い生理活性に関わる受容体の方向からの開発)や、新しい分野(遺伝子解析)について、Unmet Needsの高い領域を考えてみると、癌、アルツハイマー、重篤なアレルギー疾患、難病などがこれからの開発領域と考えられる。
一方新薬開発のコストはどんどん高騰している(図1)。新薬の研究開発で必要な、薬物標的の同定→→→臨床試験→承認申請に至る流れ(図2)を考えると、高騰はやむを得ない面もある。このため創薬を続けていくために必要となる研究開発費の負担能力を考えると、M&Aなどの手法で分母を大きくする必要のあることが明白である。
図1
図2
3.ユーロジンの開発にあたって
ベンゾジアゼピン系のトランキライザーを1960年代にロシュ社が日本市場に投入した。当社も対応するべく研究を開始したが、上司に「文献は正しいとは限らない。自分の目でたしかめるまでは信用するな。だからまず自分の考えで実行すること。文献調査は後からでも良い。」といわれた。研究の結果ユーロジン(エスタゾラム)(図3)という高活性新規誘導体を開発できたのだが、ここで上司の言葉が役に立つこととなった。ロシュは我々がエスタゾラム合成の中間体として合成した2-ヒドラジノベンゾジアゼピン誘導体を、我々とは別法で既に合成したことが報告されていたのである。しかし我々のものと物性が異なるので、ロシュ法を追試してみたところ、彼らが7員環化合物と報告した化合物は実際には8員環の構造で、薬効も認められないことが判明した。したがってロシュによる特許出願もされていなかった。
図3
また、アップジョン社は武田より3ヶ月ほど遅れて同じ骨格の化合物を出願していた。特許係争の結果、不合理な特許制度によりアメリカの権利はアップジョンのものとなったが、欧州は武田が権利を持ち、日本は製造法特許の時代だったので、お互い自由に製造できるという結果となった。我々もアップジョンが開発したハルシオンは当然合成しその薬効がユーロジンを上回ることは把握していたが、一見「鈍」な選択ではあったが、作用が穏やかで副作用がより少ないと考えられるユーロジンをあえて選択した。そして何よりも、上司の言葉通りになったことは驚きであったが、ジアゼピンの本家本元であるロシュが大きなミスをしたという「運」に恵まれた創薬であった。そして、物質特許のない時代に新規化合物を特許化し、医薬品として開発するには並々ならぬ「根」が必要だったことは言うまでもない。
4.糖尿病治療薬の開発にあたって
2型糖尿病治療薬であるアクトス(ビオグリタゾン)の創薬についてお話する。研究には実験動物が重要であるため、糖尿病を発症すると報告されたKKマウスを名古屋大学から1963年に入手した。しかし入手したマウスは自社では糖尿病を発症しないため検討の結果、高カロリー食を与えると太って高血糖となりインシュリン値も高いマウスを得ることができた。この結果に意を強くし、KKマウスと肥満遺伝子を持ったマウスを交配することによりKKAy マウスの作製に成功した。このマウスはインシュリン抵抗性(インシュリンは分泌されているが抹消での働きが十分でないため耐糖能に異常が生じ糖尿病を発症する)を持つことを示し、KKAyマウスを用いてスクリーニングを開始した。また、実験動物についてはさらに研究を続け、耐糖能のやや悪いラット(Wistar Kyoto)に、肥満発症遺伝子を持ったZucker fatty ratを交配した結果、1981年に肥満糖尿病ラット、Wistar fatty(図4)を確立することができた。なお、このラットではホモ接合体のみが肥満糖尿病を発症するが、このラットは生殖能力が低いため、ヘテロ接合体であるリーンラット同士を交配し、1/4の確率で生まれる肥満糖尿病ラットを使用せねばならず、手間がかかり、安定供給には多大な労力を要する。
図4 糖尿病性肥満ラット
KKAy マウスによるスクリーニングで見出されたシグリタゾンは臨床第二相試験の段階で残念ながら開発中止された(1983)が、後継化合物としてピオグリタゾン(図5)の開発に成功した(1999)。ピオグリタゾンの薬効評価にはKKAyマウスとともにWistar fattyラットが極めて大きな役割を果たした。ピオグリタゾン発見の経緯を次に述べる。
図5
結果的に大きな回り道をしたことになるが、シグリタゾンが臨床試験に入ったことがピオグリタゾン発見の端緒となった。シグリタゾンの臨床試験を行うにあたって必要な代謝物研究の過程で、水酸化された化合物がシグリタゾンよりも強い活性を有することが分かった。そこでドラッグデザインを最初からやりなおすこととし、ピリジンやオキサゾール誘導体など、シグリタゾンよりも少し親水性の官能基を導入した化合物を数多く合成し、KKAyマウスでのスクリーニングを続けた。その結果発見したのがピオグリタゾンであるが、この化合物は活性が最も強かったわけではなく、活性は弱くとも副作用との間のsafety marginの最も大きい化合物を選ぶという、ユーロジンを開発したときと同じコンセプトに則り慎重に選ばれたものである。
思えば1963年にKKマウスを導入したときから始まった新規糖尿病薬が世の中に出るまで36年間を要したことになる。この過程には開発そのものが崖っぷちに立たされる苦境を何度も経験したが、持ち前の「鈍」と「根」を発揮し、「運」も呼び込んでピンチを乗り切ることができた。特にアップジョン社が、我々の研究に強い興味を示し、共同開発を行ってくれたのは、大変幸運なことであった。彼らによればアメリカにはWistar fattyラットのような体型をした糖尿病患者がたくさんいるのだという。アップジョン社は武田の糖尿病薬研究や臨床開発の後押しをしてくれたばかりでなく、自らの手で1989年に米国でピオグリタゾンノ臨床試験を開始した。しかし何故かアップジョン社は途中で開発から手を引いてしまったため、武田は臨床試験を引き継ぎ、やむを得ず単独で開発を進めねばならなかったが、1999年に日米、2000年に欧州での販売に漕ぎ着けることができた。この経験により武田は海外での開発力を身につけることができたばかりでなく、このブロックバスター製品から得られる利益も独占できたのである。
武田の真のグローバリゼーションはここから始まったと言っても過言ではない。一方、我々にとっては恩人とも言えるアップジョン社はどこかに「鈍」や「根」が欠如していたのであろうか。それだけが理由ではないだろうが、その後アップジョンはM&Aによりファルマシアに吸収され、さらに現在はファイザーに吸収合併されるという憂き目に会っている。
5.創薬に王道はあるか
大切なこととして、①テーマ設定の新規/先見性、②化合物評価方法の設定、③構造最適化能力(コンピュータに頼りすぎず直感を大切に)、④研究者は評論家であってはならない(理屈よりセンスと実践)を上げることができる。しかし、創薬に王道はなく結局は研究者ひとり一人のセンスと粘りにつきると思われる。
最後に、「運・鈍・根」に「感(勘)」を加えて、講演の結びとさせていただく。
Q&A
Q 中国や韓国の創薬に対する実力はどうか。また実情は。
A 新薬開発力は不足しているが、確実に有機合成の力はつけており、日本の会社も特に中間体を中国で作らせる例は多い。中国では人口も多いので自ら創薬したいと考えている人たちは多く、今後日本にキャッチアップしてくるかもしれない。韓国は薬の市場そのものが日本の1/10ほどしかないこともあり、お金のかかる創薬を自ら行うより、出来上がった薬を導入した方が安上がりという考えが今のところ主流のようだ。しかし、日本では市場性などの理由で開発を断念したものであってもよいので、手ごろなものがないか探していると聞いている。
Q ピオグリタゾンは正常な血糖値を下げないと言われるが、どのように考えるか。
A その通りである。これまでの糖尿病薬としてはインスリンそのものを使うか、すい臓からインスリンを分泌させるSU剤などが主流であったが、インスリンが出すぎて低血糖を起こすという重大な副作用が避けられなかった。ピオグリタゾンでは元々患者さんの持っているインスリンの利用効率を上げるのが主作用なので、インスリンは必要量しか分泌されず、低血糖を起こさないと考えられる。動物でも正常なマウスやラットの血糖には全く影響しないのに対して、インスリン抵抗性が強く、血中インスリン、血糖値ともに高いKKAyマウスやWistar fatty ラットには極めて有効なのが最大の特徴である。逆にこれらの動物にインスリンを注射しても文字通り焼け石に水で、血糖は全く下がらない。
文責 藤橋雅尚、監修 目黒寛司