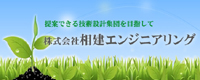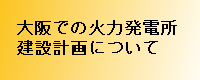日本の農林水産業の課題と環境保全 ~そのために技術士に何が出来るか~
環境研究会総会 会員講演 日 時;2019年5月16日(月) 18時50分~19時40分 講演2:日本の農林水産業の課題と環境保全 講 師;綾木光弘 技術士(森林、総合技術監理部門) はじめに 私は技術士事務所、大阪府立大学勤務(産学連携コーディネータ)、農業の三本柱で活動をしている。日本の農林水産業は多くの課題を抱え深刻な状況に陥っている。その現状と課題について概観し、課題解決と環境保全のために技術士として何ができるかについて考えてみたい。 1.日本の農林水産業の産業推移と現状 日本の全産業がGDP550兆円/年ぐらいの規模の中で、農林水産業を全部合わせてもグラフに乗らないくらい少なく、名目GDPに占める農林水産業の割合は1%にも満たない。一次産品の貿易についても存在感がなく、自給率は40%程度である。一次産業の就業者は300万人を切っている。 2.農林水産業の課題 農林水産業全体の課題として次のことが言える。 ①売上規模が小さく、収益性が低い、従業者の収入が低い、輸出入規模も小さく海外との競争力も弱いなど、産業としての存在感が不足している。 ②産業従事者の平均年齢が高く、新規就労者が少ない。過疎地に多く立地しており、経営体あたりの規模が小さい。 ③不規則な労働環境で、劣悪な労働環境も多い農業の現状と課題 1)農業の現状と課題 農家世帯員数、農業就業人口ともに大きく減少している。カロリーベースの食料自給率の推移をみると40%を切っている。ただ、平成10年度あたりから横ばいとなっており、これから増加に転じるという気配もある。 2)林業の現状と課題 林野面積は24.8万?であり、国土面積(37.8万?)に占める森林の割合は67%である。うち、人工林の割合は41%で、そのうち国有林の割合が31%である。林産物では国産木材を利用する動きが出ており、まだまだ数値的には小さいがこれからが期待されている。林業の産業規模は5,000億円にも満たず、非常に小さい。 日本の人工林の齢級構成は、昭和41年度から平成24年3月にかけて、伐採可能な木がどんどん増えている。年間1億?の蓄積増であるが、年間使用量が0.3億?で蓄積量がどんどん増えている。いいことではあるが、一方で、木が老齢化すると二酸化炭素の吸収能力が下がってくるので、このままいくと問題になってくる。 森林の多面的機能の評価値では合計75兆円と非常に大きな規模となっている。二酸化炭素吸収、化石燃料代替機能があり、表面浸食防止機能、水質浄化機能などが特に大きい。一方で、マーケットで取引される林産物は6,700億円程度で非常に少ない。 3)水産業の現状と課題 漁獲生産量は、世界では1984年から2015年にかけて大きく伸びているが、日本は大きく減少している。 排他的経済水域面積は447万?で国土(37.8万?)の約12倍である。 3.農林水産業と環境保全 1)環境保全に対する農業の役割 農業は、里山、田畑の景観保持を通じて環境保全に貢献しており、都市近郊で舗装されていない田畑はヒートアイランド現象の防止に寄与していること、里山を通じて生物多様性の維持、促進に寄与しており、都会人の癒し、リクリエーションの場所提供などの役割を果たしている。 2)環境保全に対する林業の役割 国土の7割弱が森林であり二酸化炭素吸収能力アップに貢献している。これにより、京都メカニズムを活用して京都議定書の達成成立に寄与した。 3)環境保全に対する水産業の役割 森林に比べて水産業は、環境保保全に果たす効果が明確でないことが課題である。例えば海藻がどのように環境保全に役立っているのか、二酸化炭素吸収にどう役立っているのか、酸素排出にどう役立っているのかなどがしっかりと分かっていない。 4.そのために技術士に何ができるか 日本技術士会近畿本部で農林水産部会が発足した。現在約40名が加入している。 そのための中期的な課題として、人口の都市集中是正、限界集落等改善、獣害等の防止、海外からの訪問者を里山・森林・海洋へ誘引することに取り組む。また、長期的視野に立った課題として、老齢化対応、家族制度の崩壊の立て直し、若者に希望を与えられる社会創造、国土災害の抑止、潜在的資源掘起しと有効利用に取り組むこととしている。 また、国土防災・国土維持のための協力・貢献、技術士他部門との連携、技術士と産学官連携においてマッチング機能、接着機能を果たしたいと考えている。 そのための一つの機会として大阪万博がある。日本技術士会近畿本部として技術士の存在感を示し、知名度アップを目指して、独自パビリオン又は付属パビリオンの設置、展示ブースの設置、展示会後の農林水産業特区の設置などの有効利用を検討する。 『日本の農林水産業、その原風景の今と未来』をキャッチコピーとし、命輝く未来社会をデザインするという内容で7次産業化を前面に出したブースづくりを考えていきたい。 <参加者からの質問とコメント> 質問1 日本の農林水産業が小規模で家族経営のものが多いということであるが、一国一城の主ということでうまくまとまらないという面もある。小さいままで生かしていくという観点もあると思うがどうか。 コメント1 一時、農林水産省が政府の方針として規模を大きくする方向を打ち出したが、最近少し方向性が変わってきている。規模を大きくすることが一次産業の活性化、育成につながるか疑問もある。例えば、全体の2割から3割を大規模な企業体にし、従来の小規模経営は食糧危機に対するバックヘルプという役割も考えて両方の育成ということも大事なのではないかと考えている。 質問2 農林水産業の活性化というと収入を上げるというような話が多いが、地産地消とか自給などというのが将来の姿かなと思っている。講演者が農業を含む3本柱で活動されているのがまさに将来の姿かなと思う。都市で二日間活動して農業を二日間するというようなダブルワークとかトリプルワークで充実した生活をして100年程生きるという生き方がある。そのような考え方についてどう思うか。 コメント2 都会で週の半分働いて、週末は田舎で活動するという生活が素晴らしいかは、私にはわからない。私は都市立地で農業をしており、自分の与えられた状況の中で自然な形でやっていきたい。そこに人間の価値観が入ってくる。そういったことを大事にして人間の生き方を求めていきたい。 質問3 非常に夢のある講演であった。今から10日前に豊岡市のコウノトリの里に行ってきた。そこでは農薬を使わずドジョウや魚をコウノトリが食べても害がない。そういう農業が一つの行き方かなと思った。お米なども少し高いが、健康に良いということで私も少し購入してきた。やはり美味しい。大農家で農薬などを飛行機で撒いて大量生産を行うのは健康的に悪い。ただ、価格が安い。そのような大量農家のやり方とコウノトリの里のようなやり方についてどう思うか。 コメント3 コウノトリ米とかを販売している。無農薬で栽培するといったときに、最初は農家の反発があった。それを乗り越えて無農薬で栽培すると売れるということである。日本の農業はアメリカの大規模農業のようなものにとても太刀打ちできない。やはり、日本の国土の特徴を生かした、きめ細やかな、国土にあったやり方を進めていかなければならないと思う。技術士もそういった農業をサポートしていかなければならない。 質問4 世界はスマート兼業の方向に明確に舵を切っていると思う。来年度からはご存知のように5Gが始まる。日本だけとかローカルだけということではなくなり、ごっそり県単位、地区単位で情報化が進む時代が目の前にある。技術士会は非常に優秀な専門技術を持った技術士の集まりである。世界からは大分水をあけられているが、是非、旗振りをしていただいて、後れをとらないようにがんばってほしい。 コメント4 特に農林水産業では、スマート化ということでデータを使うことが遅れている。少しでも技術士として貢献していく必要があると思う。日本の特質を生かした農業、スマート化をサポートしていきたい。 (文責:大西政章、監修:綾木光弘)
場 所;大阪市アーバネックス備後町ビル3階ホール
~そのために技術士に何ができるか?~
農業就業人口は160万人程である。新規就農者が少ないが、雇用労働者が結構多い。外国人雇用がこれから増える可能性がある。新規就農者において39歳以下の人が多くなってきているのが明るい兆しである。
農家の総所得は年間400万円程度で、内農業所得が120~130万円程度である。ただ、会社組織にすると主業経営体総所得が700万円ぐらいになる。
農業の課題をまとめると、就農者の高齢化、所得が低く兼業で生活している就農者が多い、限界集落の増加や離農者の増加、国際的価格競争力の低さ、農業の魅力アップ、産業基盤の底上げなどがある。
林業の経営体は、山を持っている林家と呼ばれる人が80万人ほどで多いが、実際に林業を経営している人は少ない。林業従事者は非常に少ない。
日本の木材自給率は、平成13年に20%を切り、今は上がってきている状態で30数%となっている。輸入丸太は減少しており、特に東南アジアからは自然保護などの環境問題があり非常に減少している。
林業就業者の高齢化率は一時30%となったが、今は若干減少してきており、若年者の率が上がってきている。
日本の林業・木材業の課題として、まず森を活用できていないことである。また、林業の生産性が低い。
漁業者・漁船単位の生産量では、アイスランドやノルウエー、ニュージーランドなどが極端に高く、日本は非常に低い。
漁労所得は年間300万円程度。消費量は平成13年がピークで、それ以降減少している。
水産業を成長産業とするには、資源を持続的かつ最大限に利用できることが必要であり、そのためには、まず資源情報を収集し、資源評価を行い、資源管理をしっかり行うことが重要である。
水産業の課題とその解決に向けて重要なことは、資源保護が計画的にできていないこと、捕獲方式として家族単位が多く小規模の船舶であること、養殖技術の向上、資源捕獲と資源保護の相乗効果が発揮されていないことである。
農林水産業の労働者比率は1945年時点で55%から現在3.1%となり、農林水産業の産業規模は年間11兆円で全産業の1.3%となっている。現状は、とても日本の基幹産業とは言えないが、国力の基本的要素を満たす一次産業こそ国の基盤的産業であるとの考えから、農林水産部会は、一次産業全体として環境保全、潤いのある農山漁村の保持、自給率アップ、国際競争力強化を目指して取り組んでいくこととしている。
環境保全を考えながら日本の一次産業を復活させ、日本、世界の諸課題を解決していくために頑張っていきたい。 講演会風景
講演会風景