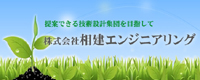脱炭素の潮流と、国内外の動向
近畿本部登録 環境研究会 第109回特別講演会
講演 脱炭素の潮流と、国内外の動向
日 時: 2024年4月16日(火)18:30~20:00
場 所: アーバネックス備後町ビル 3Fホール + Web(Zoom)
講 師: 福嶋 慶三 氏
環境省近畿地方環境事務所 地域循環共生圏・脱炭素推進グループ
環境対策課長 兼 地域脱炭素創生室長

1.気候変動とカーボンニュートラルに向けた国内外の動向
2021年にグラスゴーで行われた気候変動枠組み条約COP26 では、長期気温上昇目標は1.5℃以内に抑える旨の達成に向けた確認がなされたが、実態は目標に向けた排出パスとは大きなギャップが存在し、世界全体で1.5℃達成に向け、野心的な温室効果ガス排出削減が求められている。
我が国では2050年カーボンニュートラル(以下、CN)実現に向け、GX(グリーントランスフォーメーション)実行会議が2022年7月の設置、2023年2月にGX実現に向けた基本方針が閣議決定、同年5月にGX新法が成立、今後10年間で150兆円を超える官民投資が行われる予定である。
2.企業の動向 ~大企業・中小企業・金融機関の脱炭素~
このような背景を受け、企業では脱炭素経営が重要課題と捉えられており、大企業のみならずサプライチェーン・バリューチェーンの観点から中小企業を含めたすべての企業に取組みが求められている。金融機関においても地域の企業とともに脱炭素化を自らの重要経営課題として企業との連携・支援に着手し始めている。また、地域の金融機関と国の連携も進んでおり、環境省近畿地方環境事務所では、近畿の地銀(2行)のほか、近畿地区信用金庫協会や信金中金大阪支店・神戸支店との連携協定を結び、金融機関の営業マン向けの研修等を実施している。
3.地域主導の脱炭素化~地方から始まる次の時代への移行戦略~
2024年3月29日現在、「2050年CO2排出実質ゼロ」を1078の自治体が表明している。この数は全国の自治体の約2/3にあたる。地域脱炭素の意義は、地域の経済・雇用や循環経済のみならず住居やインフラの快適性や防災・減災への課題の解決に貢献できることにある。国の近畿地方省庁支分部局では連携して2021年11月にきんき脱炭素チームを発足させ、地域脱炭素に向けた取組みを進めている。
また、2030年度までに少なくとも全国100か所のゼロカーボン・エリアである「脱炭素先行地域」をつくり、2050年を待たずに先行して脱炭素を達成するための取組みや支援を行っている。全国では既に73件が選定されており、近畿ブロックでは滋賀県米原市や大阪市等の1県10市が脱炭素先行地域に選定されている。地域脱炭素は環境視点だけでなく「まちづくり」全体の視点が必要であり、大阪市の例では中心のCNストリート「御堂筋」が計画されている。
4.市民をどう巻き込むか ~脱炭素に向けた行動変容~
脱炭素社会に向け、日常生活から行動を変えることが大切である。例えば、スナック菓子は、地球の温暖化と関係があるとの説明があった。スナック菓子の製造過程で使用する植物油はやしの木(実)から採取される。やしの木を栽培するインドネシアでは元々あった森林を伐採し、アブラヤシ大規模農園に形を変え、より安価な油を生産している事例があり、その結果、もともとあった森林が伐採され、地球の温暖化や生物多様性の喪失につながっている。これらを防止するために持続可能な方法で生産するRSPO(持続可能なパーム油のための円卓会議)認証の植物油を使用されるようになってきている。
地球温暖化という言葉は知っていても、脱炭素のために何を使用すればよいか分からないなど、具体的な行動に結び付いていないということがある。使用するエネルギー節約やマイバッグを使用してごみを減らすこと、脱炭素型商品の買い物など、日常生活の中での行動を変えることも大切である。
Q&A
Q1.講演の中にあった自治体向けの脱炭素まちづくりアドバイザー制度に登録する方法について詳しく知りたい。
A1.環境省のホームページで登録や申し込みに必要な事項等は確認できるので、ご確認いただきたい。
https://policies.env.go.jp/policy/roadmap/platform/?tab=03
Q2.中小企業が実際に脱炭素に取り組んでいるかどうか、どのような方法・手段で検証できるのか。
A2.大企業向けに世界的な認証方法であるSBT(Science Based Targets)がある。
https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/files/SBT_syousai_all_20210810.pdf
SBTとは、パリ協定と整合する2℃目標に向けて企業が行う温室効果ガス排出量削減目標の取組みを検証する制度である。中小企業向けにもSBT制度が公表されており、この認証を取得しているかどうかでわかる。
中小企業がSBT認証取得する意義とは?わかりやすく解説!
- 一般社団法人 環境エネルギー事業協会
(ene.or.jp)
おわりに
新たな国民運動「デコ活」、大阪府の取組み「おおさかCO2CO2(コツコツ)ポイント」、「気候市民会議」を考えるワークショップ等の紹介があり、脱炭素への社会の取組について参加者が再認識する内容であった。
また、脱炭素に向けたクイズで参加者との双方向のやり取りが行われ、わかりやすい解説を交えた講演であった。
(文責 奥村勝、綾木光弘 監修 福嶋慶三)