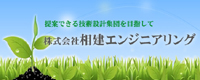世界の海水淡水化に貢献する日本の膜技術
近畿本部 二組織合同(化学・繊維) 2024年3月度講演会
メインテーマ:健康・安全・環境に係る技術力の発揮
講演1 世界の海水淡水化に貢献する日本の膜技術
日 時: 2024年3月9日(土) 13:30~17:00
場 所: 近畿本部会議室 TeamsによるWeb併用
講 師: 栗原 優 氏
工学博士 東レ株式会社フェロー、国際脱塩協会理事
1.世界の水資源問題と逆浸透(RO)法
水資源問題はセキュリティー面からも健康・安全・環境に関わる世界的な重要課題である。水処理技術には旧来のろ過法の他に蒸発法と膜処理法があるが、蒸発法に比べて膜処理技術は高品質・高速処理・省エネプロセスであることから21世紀の基幹技術になり得る。 米国では1960年代から宇宙開発と同時に淡水化技術の開発が進められた。同時期に日本でも官・学・産でRO膜の研究開発が始まった。
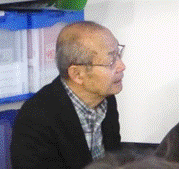 栗原 優 氏
栗原 優 氏
セルローストリアセテート(CTA)中空糸膜を束ねたエレメントと架橋芳香族ポリアミド(PA)平膜をスパイラル状に巻き付けたエレメントが主なもので、開発当初は前者が主流であったが2010年以降は90%以上が後者となっている。
講師が開発主体となったPA平膜の合成方法、膜の細孔や表面等の構造解析およびそれら微細構造と透水性能との関係について解説された。
2.国家支援の研究競争と“Mega-ton Water
System”
2001年以降政府や経団連で海水淡水化等の研究開発や水問題の重要性を提言されてきたが、2009年にオールジャパン体制として日本の新成長戦略(基本方針)に水ビジネスが組み込まれ、また“Mega-ton
Water System”プロジェクト(2009-2013年)が講師を中心研究者として立ち上げられた。「持続可能な海水淡水化と再利用」をビジョンとし、「エネルギーの削減(20-30%)」、「低環境負荷(薬品使用の削減)」、「造水コストの削減(50%)」をミッションとし、100万㎥/日(4百万人分に相当)の造水を目指した。膜の精密分析によって表面形態と透水性の相関を見出し透水速度や脱塩性能といった性能を向上すると共に、塩素を用いない前処理技術の開発によりバイオファウリングの課題を克服した。
3.RO膜の普及状況と今後の課題
中東での淡水化事業は蒸発法からRO膜法へ移行中であり、海水淡水化プラントのシェアは日本企業(東レ、東洋紡、日東電工)が過半数を占め、米国企業(Dupont、Dow)は減少しているが、近年は韓国(LG Chem)が伸びている。海水の総合利用の面では淡水化のみならず、濃縮海水に含まれるミネラル(Mg,Br,K,Ca)の利用が検討されている。基礎技術の面では専門誌への投稿論文数で日本の順位が年々低下しており研究開発力の維持と強化が望まれる。
質疑応答
会場から膜モジュールの交換頻度とプラントの稼働寿命に関する質問やグリーン水素とRO膜との関係に関する質問があり、活発な意見交換がなされた。
文責:太田 昌三、監修:栗原 優