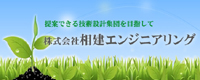カーボンリサイクルシンポジウム パネル討議
著者: 中田将裕 / 講演者: 伊藤 雄二、谷口 育雄、西中 久雄、赤木 知裕、高岡 直樹、吉田 悟 / 講演日: 2024年07月13日 / カテゴリ: 環境研究会 > 講演会 | 化学部会 > 講演会 / 更新日時: 2025年03月15日
近畿本部 化学・繊維・農林水産部会、環境研究会 合同講演会
メインテーマ: カーボンリサイクル(CO2分離回収・有効利用技術)
3.パネル討議: (小型)発電所排ガス用途の技術評価
日 時: 2024年7月13日(土) 13:00~17:00
場 所: アーバネックス備後町ビル3階 ホール
座 長: 伊藤 雄二氏 化学部会長
討議参加: 谷口 育雄氏、西中 久雄氏、赤木 知裕氏、高岡 直樹氏、吉田 悟氏
はじめに
本討議では、基調講演で示された「CO2膜分離技術」を利用して、火力発電所排ガスから得られる濃厚CO2を、植物工場・化学肥料製造・合成ガス燃料製造等に利用した場合(図1参照)の技術評価を試みる。天然ガス燃焼による火力発電所を想定し、分離膜により90%の高濃度でCO2を分離回収と仮定した。
1)一次技術評価(定性):濃厚CO2を植物工場に利用した場合の便益とリスクについて討議
 伊藤 雄二 氏 (他の討議参加者の写真は、1.2.参照)
伊藤 雄二 氏 (他の討議参加者の写真は、1.2.参照)
便益に関しては、施設園芸農家は規模が小さいところが多いため、ある程度の規模でCO2備蓄を行う仕組みができれば、相応の便益が得られると考えられる。
一方、火力発電所からの排ガスには、CO、SOx、H2Sなどの有害物質が含まれるリスクがあるが、無害化・吸着するための装置を備えておくことで、リスクを最小化することは可能である。
また、採算性の観点では、CO2分離膜法は従来のアミン吸収液法の半分以下の低コストを既に達成しており、今後も技術の進歩に伴ってコストダウンが進んでいくと予想される。
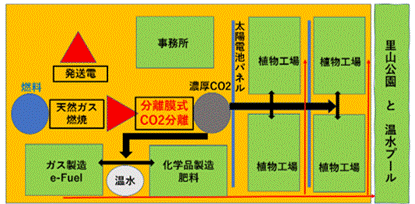 図1 火力発電所排ガスからCO2を分離回収し、植物工場等に利用する想定の例
図1 火力発電所排ガスからCO2を分離回収し、植物工場等に利用する想定の例
これらの討議において、図2のような想定質問、及び、それに対する対応についても座長より示された。また、考慮すべき国内法としては図3の各法律が例示された。
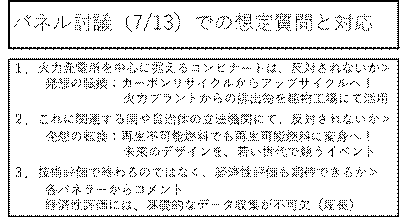 図2 想定質問と対応
図2 想定質問と対応
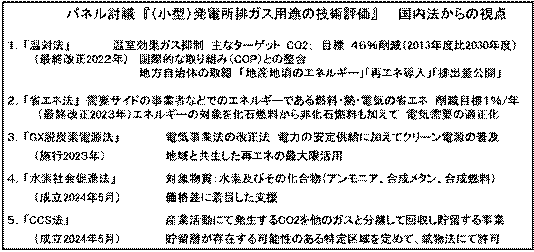 図3 国内法からの視点
図3 国内法からの視点
以上の討議結果から、定性的には本技術の有用性が示されたと考える。カーボンリサイクルからアップサイクルへの発想転換が重要となるが、その手段として植物工場が適切かどうかについては、基礎的なデータをさらに収集し、経済性評価を行う必要がある。
2)二次技術評価(定量):火力発電所排ガス利用のCCU/CCSについて定量化を行う
図4に示す基礎データを基に、本事例でのCCU/CCSについて定量化を試みる。最低限規模の火力発電所として発電量1万kWhを仮定する。CO2排出量(CCS理論値)は3万トン/年と見積もられるため、植物工場、化学肥料製造(尿素)、合成ガス燃料製造(合成メタン)のそれぞれに1万トンずつ割り振って利用することを想定する。
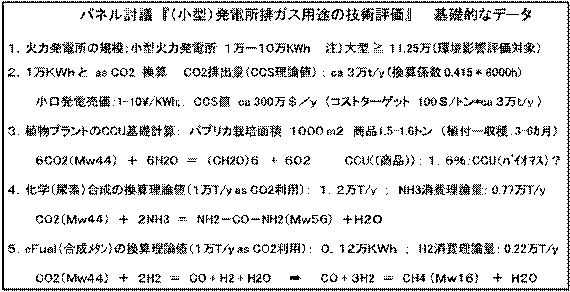 図4 二次技術評価(定量):基礎的なデータ
図4 二次技術評価(定量):基礎的なデータ
植物工場について、現状の日本でのパプリカ温室栽培での実績値から推定した理論計算により、CCU/CCSは2%程度となった(CO2→バイオマス(農産物とバイオ燃料)への転換比率)。一方、尿素合成では化学量論式からはCO2を全て反応させて同量以上の尿素が得られるため、CCU/CCSとしては100%以上が可能。合成メタン製造の場合は、10%以上(CO2投入量に比例するとして3倍の30%までは可能)と算出された。
以上から、化学肥料製造、合成燃料製造並びに植物工場でのCCU/CCS合算値としては30-40%となり、本技術評価での目標値を10%とおいた場合、合格と評価できる。
3)まとめ
今回討議したCCU/CCS値の算出が、CCUSの技術評価として興味深い手法であることが示され、上記合算値は、プラントコンビナートを提案できるレベルと見做した。個別にみると、植物工場での2%の数値は低い。ただ、世界的にみるとまだスタート台であり、生産規模の拡大などに向けた資金投入や種々の技術面での収量アップは考えられるため、伸びしろは大きい。
合成メタン製造にて10%台という評価値は、再生不可能燃料の天然ガスにとっては、その分、再生可能燃料に転換できることを示した意義は大きい。加えて、プラントコンビナート内での動力源を再生可能エネルギーで賄える可能性もある。いずれの事項についても今後の展開に期待したい。
(文責:中田将裕、監修:伊藤雄二)