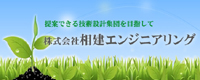カーボンリサイクルシンポジウム パネラー講演
著者: 奥村 勝 / 講演者: 西中 久雄、赤木 知裕、高岡 直樹、吉田 悟 / 講演日: 2024年07月13日 / カテゴリ: 環境研究会 > 講演会 | 化学部会 > 講演会 / 更新日時: 2025年03月15日
近畿本部 化学・繊維・農林水産部会、環境研究会 合同講演会
メインテーマ: カーボンリサイクル(CO2分離回収・有効利用技術)
2.パネル講演 4組織所属の技術士によるパネラー講演
日 時: 2024年7月13日(土) 13:00~17:00
場 所: アーバネックス備後町ビル3階 ホール
講演1 CO2分離技術と繊維(CO2回収・分離中空糸膜について)
講師: 西中 久雄 氏(繊維部門)JTCC理事長
 西中 久雄氏
西中 久雄氏
経済産業省からカーボンリサイクルロードマップが公表されている。その中にCO2分離・回収技術として吸着法と膜分離法が示されている。分離・回収コストはCO21トン当たり吸着等法では4,200~2,000円台であるが、膜分離法では1,000円台と安く、開発が加速されている。NEDOの技術開発補助事業の膜分離法技術開発では、CO2分離・回収は低コストの膜方式が有力で、平膜と中空糸膜の両方で検討が進んでおり、企業や大学での膜分離法を活用したCO2分離・回収技術と九州大学や東北大学のDAC(直接空気回収技術)に加えて、既存CO2ガス関連会社の酸素・窒素・水素やメタン分離技術も含めカーボンリサイクルについての取り組みが紹介された。
今後、CCUに向けた課題として、分離・回収に加えて最終物質までのトータルシステム構築、収率向上等が挙げられると述べられた。
。
講演2 炭酸ガス施用の栽培事例と課題
講 師: 赤木 知裕 氏(農業部門)農林水産部会幹事
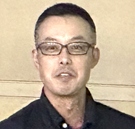 赤木 知裕氏
赤木 知裕氏
施設園芸は、ガラス温室やプラスチックハウス、ビニールシートで囲ったハウス内で、野菜、花卉、果樹 などの作物を栽培する。高度な技術と集約的な管理を伴い、農業経営の一形態として発展してきている。その一例として紀の川市あゆみ農園が行っている給湯器を利用したCO2施用による野菜の多収技術の紹介があった。施設園芸内のCO2濃度を400ppmに維持し制御することで収量アップにつながる。
オランダではCO2ガスボンベを利用した施設園芸が整備されており、日本と比較してトマト収量で5倍、労働生産性で9倍との大きな差があるとの説明があった。
今後、日本の施設園芸の拡大発展にはCO2施用等のインフラ整備と人材育成、国や自治体の支援が重要であると締めくくられた。
講演3 本気のカーボンリサイクルを考える
講師: 高岡 直樹 氏(化学部門)化学部会幹事
 高岡 直樹氏
高岡 直樹氏
国内のCO2市場は、ここ10年以上大きな変化がなく約100万トン/年である。エネルギー庁がカーボンリサイクルロードマップを公表しており、CO2排気ガスをそのまま利用する方法と分離回収する方法からなる。分離回収されたCO2は、ドライアイス製造や石油増進回収で利用されるほかにカーボンリサイクル(以下、CR)されるものに分かれる。
CRは、無機鉱物(セメント、コンクリート)、化学品(ポリカーボネート、尿素)、燃料(メタノール、メタン)などがあり、それぞれ化学品フロー図を用いて詳細な説明があった。
JOGMEC(エネルギー・金属鉱物資源機構)調査によると日本は欧米と遜色なくCR技術に取り組んでいる。また、オンサイト型、中小規模分散型等の産業間連携でCRに取り組んでいる事例の紹介があった。
講演4 IPCC/COP28とカーボンプライシング
講師: 吉田 悟 氏 環境研究会幹事
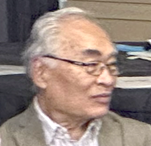 吉田 悟氏
吉田 悟氏
2023年に公表されたIPCC(気候変動に関する政府間パネル)第6次報告書では産業革命以降1.1℃の温暖化を報告している。第7次報告書は2027年頃の公表に向け取り組まれており、トピックスとして、都市、短寿命因子、CDR (Carbon
Dioxide Removal)、CCUS (Carbon
dioxide Capture, Utilization and Storage)があげられている。CDRでは海洋が温暖化に及ぼす影響が検討されている。
日本のカーボンプライシングは,他国に比べ遅れており、2023年10月に炭素クレジット市場が設立されたが、年間14万トンと取引高は低い。一方、GX成長戦略が2023年2月に閣議決定され、2050年のカーボンニュートラルに向けて20兆円の債権をもとに民間に10年間で150兆円資金を投じてCO2削減の技術開発計画の紹介があった。
(文責: 奥村勝、監修:西中久雄、赤木知裕、高岡直樹、吉田悟)