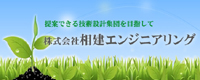社会活動による里山整備とその活用
近畿本部登録 環境研究会 第112回特別講演会
社会活動による里山整備とその活用
日 時: 2024年11月30日(土)14時00分~16時00分
場 所: アーバネックス備後町ビル3Fホール + WEB
講 師: 熊谷 哲 氏 兵庫県立大学名誉教授
理学博士
NPO法人はりま里山研究所理事長
1.私の生涯学習 その1(大学・大学院時代)
大学入学後大学紛争でキャンパス内に入れず。放射線や放射能に興味を持ち大学3年時に第1種放射線取扱主任者の国家資格を得る。大学のゼミで原子力の危険性を聞き、放射性物質への興味が減少し、分析化学へ方向転換。
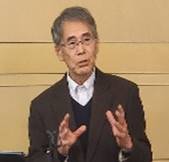
2.私の生涯学習 その2(姫路工業大学・兵庫県立大学(統合)時代)
・工学部で分析化学研究のため、プログラミング(独学)やPCの組み立てを行う。
測定器のデータを読み込み処理や表示を行うプログラミングを作成。(30代)
・大学の講義を、ネットを介して行う取り組みを始め地域との関わりに目覚める。(40代)
・大学の研究室での実験などに物足りなさを感じ環境への興味を持つ、大学に人間環境学部が発足と同時に学部間移動し、分析化学→環境分析化学→環境教育へと進む。
・西播磨地域ビジョン委員会専門委員として地域活動を学ぶ。(50代)
・定年10年前、環境と地域活動をつなぐ里山整備を開始し、リタイア後の仕事づくりを考えNPO法人の運営、エコヒューマン地域連携センター長などを経験し学んだ。(60代)
3.私の生涯学習 その3 リタイア前後 里山整備とNPOはりま里山研究所
・2006年に自宅裏の里山を購入し、里山整備を開始。2016年が定年なので10年かけたらできるだろうと目算。
・化学が専門、情報も少々だけれども、植物を中心とした里山は専門外。またも独学で里山関連の書籍を多量に読み里山整備の研究を進める。
・整備方針を決め、切る木と残す木を決め、判別すればよいと走りながら考え学んだ。
・10年経つと心地よい里山環境に整備が進んだ。定年後約10年は縮小のステージか?
・第2の人生を考えるきっかけをいただいたのは、商家で財を成し、その資本で55歳から全国の測量を開始した伊能忠敬。
4.不要になった里山(地域)の再資源化
燃料革命で里山が不要になり里山の荒廃が進む。高度成長期のニュータウン開発による里山の消失・都市化による里山地域の人口減、ニュータウンの高齢化、空き家問題などの問題があり、新たに地域資源としての里山(地域)の活用が必要となっている。
生物多様性と里山の生態系サービスの有用性、地域交流や遊び・学習の場としての里山の活用、憩いの場としての里山→自宅の庭と一体にした里山ガーデンとして、地域づくりに活用しようと整備を進めた。
その際の視点は、里山の文化の象徴として考えられる京都の庭と里山(例えば無鄰菴の様に東山の借景を取り込んだ庭や、竜安寺石庭の様に山と川を石と砂で表現)の佇まいを、ガーデニングの視点で活用した。その取り組みとして、里山の背景を生かした自宅の庭(熊谷ガーデン)を造った(妻はガーデニングが趣味)。その後、里山も庭の一部として拡張整備し、里山ガーデンとした
5.里山のインフラ整備と地域との連携
2006年里山整備開始、2009年ガーデニング団体と連携、2012年・2013年連合自治体と連携、2015年NPO独自で作業用の道=遊歩道として整備を進め、2020年駐車場を兼ねる姫ケ丘パークを整備した。
6.里山での保全活動と生物資源
蝶や蛾、ミヤマカラスアゲハ、オオミズアオ、クロアゲハ、ヤママユガの保全。ビオトープガーデンの、モリアオガエル、シュレーケルガエル(これらは産卵行動も確認できた)、ヒキガエルなどの生き物資源の保全。
里山原種のバラ(テリハイノバラ)のいばらの除去する場所と保全する場所をバランスよく整備し、和紙の原料となる樹木(ガンピ)の保全。アベマキとサルトリイバラ(かしわ餅の葉)保全。春の里山資源となるヤマザクラとコバノミツバツツジ、秋の里山資源としてのカマツカなどを、間伐により目立ちやすくした。
7.その他の活動の整理
里山の保全活動と薪の利用に関して、ナラ枯れへの対応(間伐作業で伐採し散策路の補修や薪に利用)、姫路市の市蝶(ジャコウアゲハの)の活用、食害対策(鹿の食害に強いガーデンづくり)、そして子供たちと大学生の居場所や学習の場を確保した校区の子供達の訪問(自然観察会に利用)の継続、大学生の学習の場として支援した兵庫県立大学のまちづくり系・建築系の20人以上の学生の参加によるツリーハウス(2011年制作:10年後の解体を条件)などを行った。
その後コロナの終息を見て2023年に、かって担当した学生と現役学生が参加して解体し、子供たちが安全に遊べる小型のツリーハウスを制作した。大学生の花活動の支援、兵庫県の中間支援事業の活用によるバタフライガーデン(蝶と共生する花壇づくり)づくり、県民まちなみ緑化事業を使った里山の教育的活用の公園化事業を行った。加えて、空き地を利用した姫が丘里山パークを、15台の月極駐車場と20台の芝生駐車場とし、芝生駐車場の周りに植栽しバタフライガーデンと桜ガーデンを有する公園として地域に開放(県民まちなみ緑化事業)。
8.手柄ザクラを通した地域創生
姫路市在住の室井博士が平成8年に発見した二重(10弁)花が咲くフタエカスミザクラ(手柄地区連合自治会が‘手柄ザクラ’と命名:2019.3.1保存樹に指定)が、手柄山に一本だけある(このさくらは移植ではなく自生していたものと考えられる)。現在弱っていて治療中であるが、この手柄ザクラを手柄地域の地域づくりのシンボルとしたいという広報の依頼を受けてプロデュースした。成果物は次である。
「あげはくんとシラサギさん とくべつなさくらの絵本(ぶん:みんつ、え:やなみ)」と「手柄ザクラのCD(歌:福永悠加)」を同時販売した。(ネット販売、CDも限定販売)
9.里山企画の事業 → 社会活動(まとめに変えて)
2016年3月 定年退職(名誉教授に)し、外部の人間として学生指導を継続しながら、NPO役員や財団理事として社会貢献活動を行っている。資金的な課題を考えて、住の面から社会を支える仕事を開始し、アパートや店舗・古民家の運営管理を行う里山企画を起業し、里山研究所を支えているが、年齢を考えると活動をどう維持していくかが大きな課題。あと10年を描きにくい と締め括られた。しかし講演会修了後も里山企画のオクタゴンの改修や里山ガーデンでの活動を、先生のFacebookに投稿され、精力的に活動を続けられている。
文責 西島信一 吉田 悟 監修 熊谷 哲