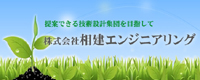激変期における「環境経営」の行方と影響
近畿本部登録 環境研究会 第113回特別講演会
(NPO法人テクノメイトコープとの共催)
演題2 激変期における「環境経営」の行方と影響
日 時: 2025年1月25日(土)13:30~16:30
場 所: アーバネックス備後町ビル3Fホール + WEB
講 師: 佐々木 正顕 氏 個人事
業主Sus-Tree(サスツリー)代表
1.本日お伝えしたいこと
本日は、個人ではなかなか全貌がつかみにくい最新の「環境経営」について、世界で何が起こっており、顧客である企業等が何を重視しているかを中心に、ざっくりとイメージしていただけるように「全体像」を整理して紹介したい。

先進企業が、経営戦略としてどの事業領域に注力するかを長期視野で判断する際に参考にしているのは、時代の変化や世界の価値観の変化であるが、その傾向がつかめるのが「ソフトロー」と呼ばれる分野である。(昔は、排水規制値等を決めた法律や条例といった「ハードロー」が重視されていたが、それらは社会害を防ぐために定められた遵守して当然の最低基準に過ぎず、新たなビジネス機会と差別化のためにはもはや役立たない)。
本日は固まりつつあるハードローの方向性や、最新のソフトローの動き、その背景としての世界の価値観の変化などを紹介する。
2.社会(経済・政治)の激変
2-1 トランプ旋風
ここ数日、ニュースはトランプ就任によるパリ協定離脱や化石燃料生産増大などばかりで、これまで新しい時代の指標としてとらえてきた脱炭素などの「環境経営」の要素は、無意味になるかに感じている方も少なくないと思われる。しかし、「反環境論」に関しては、発言のインパクトに振り回されず、石炭産業活性化による地域経済浮上なのか、政敵非難の材料か、何をDeal(取引)しようとしているのか等、その「意図」を読み解く冷静さが必要である。
たとえば、民主党バイデン政権の政策の軸であった「インフレ抑止法」を攻撃しても、実際には共和党支持州で、風力発電への投資などその恩恵が大きかったことから、修正して運用する見通しとの見解が多い。莫大なお金の動いているESG投資についても、それを解消(米国への資金が他へ流れることを意味)するはずもなく、一部の是正やESG項目と収支の関係証明強化等に留まる可能性が高い。何より米国は州知事の権限が強いので、州ごとの施策分断がされながらも「環境」は影響力を発揮動きし続ける。
2-2 日本での2026年排出量取引制度義務化
既に米国も含めて世界で動いている排出量取引制度が、法律によって、一定規模以上の企業に義務付けされることが決まっている。すでにカーボンクレジット価格は急騰しはじめ、企業はそれに向けた準備を進め、世界もカーボンクレジットマーケット開設など産業化が進んでいる。トランプ氏を応援したマスク氏のテスラ社が実は排出量取引により大きな利益を上げているように、制度としての波及は小さくない。
2-3 生成AIの拡大とゼロエミッション・データセンター(DC)
世界中で進む生成AIは膨大な電力に支えられており、そのために世界のAI企業は電力調達に注力している。この分野では「24/7CFE」という時間単位のCO2排出ゼロが求められているために、小型原発や再エネ型DCに取り組んでいる。
3.サステナビリティー情報開示の拡大
3-1 EUの「CSRD」と「ESRS」/ 事業プロセス全体での対応拡大(環境と人権の統合)
この分野で世界をリードするのはEUであり、米国動向とは別にこの動きも注目しなければいけない。開示ルール策定を介してESG投資の膨大な資金を呼び込んできた。その中で「企業サステナビリティー報告指令(CSRD)」というルールの大枠と詳細基準「ESRS」が動きだし、EUに関わる日本企業は漸次対応を求められる。この分野では、企業が環境によりどんな財務影響を受けるかだけでなく、企業が与える影響についてもその重要性を考えることが求められる。また、より広い事業プロセス・バリューチェーン全体での対応も必要という意味で、該当企業にとっては負担が大きい。
3-2 日本でのサステナビリティー情報開示の動き
日本においても世界的な「国際サステナビリティー基準審議会(ISSB)」の基準に準じた国内基準(SSBJ)の義務化が始まる。世界標準に合わせていかないと日本に資金が流入しないためであるが、これまでの部分的開示と比べて有価証券報告書での義務化につながるもので影響は大きい。複数の開示基準の併存は複雑だが、これらの集約が進むまで当面はCSRDとSSBJ対応は避けられない。当面は、世界基準の概要を把握するアンテナを張っておきたい。
4.「ネイチャーポジティブ経済」の浮上
企業の経営戦略策定に影響を与え始めているもう一つの潮流が「ネイチャーポジティブ」である。多くの企業の事業活動は自然のめぐみ(生態系サービス)に依存しているが、自然は劣化しており、このまま放置すると企業活動だけでなく市民の生活にも支障がでかねない。そのために影響力の大きな企業が単に生態系のこれ以上の低下をさせないだけでなく、回復(自然再興)に向けた活動を義務付けられる動きを示している。
これを経営の仕組みとして位置付けたのが「自然資本」という考え方。従来の財務情報は製造資本などの「有形資産」が付加価値の源泉とされてきたが、今まで金額化できなかった自然を算定技術の進化で金額化し、財務要素として経営に組み込む流れである。
5. 激変時代の「環境経営」との向き合い方
「反ESG」情報を表面的に捉えず、理解を怠らず走りながら対応を考えることで、長期視点での環境情報を自らの技術領域深化の参考にし、自らの顧客とのコミュニケーションを通じて重点領域を取捨選択しながら、プロとしての信頼を高めていきたい。
(文責 佐々木一恵 鈴木秀男 監修 佐々木
正顕)