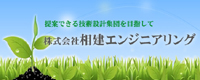関西万博展示での循環型食料システム
近畿本部登録 環境研究会 第113回特別講演会
(NPO法人テクノメイトコープとの共催)
演題1 関西万博展示での循環型食料システム
日 時: 2025年1月25日(土)13:30~16:30
場 所: アーバネックス備後町ビル3Fホール + WEB
講 師: 増田 昇 氏 大阪府立大学名誉教授・LA まちづくり研究所主宰
1.2025年大阪・関西万博と大阪ヘルスケアパビリオンの概要
2025年4月13日から184日間にわたって開催される大阪・関西万博は「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに据えており、コンセプトは未来社会の実験場として次世代技術・社会システムの実証である。大阪ヘルスケアパビリオンは、オール大阪の知恵とアイデアを結集させ、訪れた人々が「いのち」や「健康」、近未来の暮らしを感じられる展示を実現するとともに、大阪という都市の活力・魅力を世界のより多くの人々に伝えてくことを目的としてREBORNをテーマに掲げている。本パビリオンは日本政府のパビリオンに次ぐ規模である。
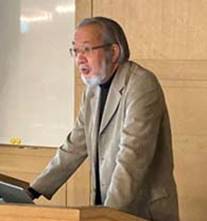
本パビリオンに設置されるいのちの湧水(いずみ)「地球儀型アクアポニックス」は、SDGs社会の実現に貢献する持続可能な次世代の循環型食料生産システムのショーケースである。
2.アクアポニックスに関する解説と開発の背景
アクアポニックスとは、1970年代より米国で研究が始まった水産養殖「Aquaculture」と水耕栽培「Hydroponics」を融合させた持続可能な循環型農業生産システムである。90%の節水と物質循環による高効率の食料生産が可能となる。
地球規模での気候変動による異常気象や砂漠化の進行、紛争や経済ショックによって食料や水の危機が進んでいる。循環型食料生産システムであるアクアポニックスは21世紀の食料・水問題の解消に貢献する。また、マグロをはじめとするサバ科魚類など、商業的に重要な水産資源の激減が、乱獲や生態系の破壊、そして気候変動などの影響により引き起こされている。陸上養殖システムであるアクアポニックスは21世紀の海洋資源の保全にも貢献する。
植物工場を含む我が国の施設農業の現状は、園芸用施設の設置実面積が約5万haである。そのうち高度な環境制御装置を備えている植物工場は約50haであり、電気代を含めた収支効率の悪さからここ10年事業所数の増加は実現できていない。
アクアポニックスの形態としては、水耕栽培部分がハウスあるいは太陽光型植物工場からなるもの、完全閉鎖系の人工光型植物工場からなるものがあり、人工光型植物工場は、多層型栽培が可能となり土地利用効率は非常に優れているものの経営上は6割の施設で赤字決算となっている。そこで、陸上養殖と融合させることによって経営効率の向上が期待されている。
3.いのちの湧水(いずみ)地球儀型アクアポニックス
アクアポニックスの物質循環は、魚からの糞尿によるアンモニアの排泄と残餌が微生物によって硝酸塩へ分解され、植物の栄養素として吸収され、浄化された水が養殖用の水槽に戻る。本システムでは魚の餌として植物残渣で育つアメリカミズアブという昆虫を利用することによって物質循環を高度に実現している。
地球儀型アクアポニックスは6角形のコンクリート製基礎の上部に魚養殖用の4個の水槽を配置しその上部のガラスドームの中に3層の水耕栽培棚とハンギング式栽培装置を設けている。1段目は海水と耐塩性植物、2段目は淡水と機能性野菜、3段目は汽水と準耐塩性植物(ミニトマト)、4段目は淡水とエディブルフラワー(食用花)の組み合わせとなっている。各層で飼育される魚介類もテラピア、ニジマス、トラフグ、ニシキゴイ、チョウザメと多様であるが、汽水の水槽では海水魚・淡水魚の同時養殖を試みている。また、日本人になじみのない魚類に関しては高級食材となるようレシピの開発も行っている。
水槽は背面側に配管や配線等の設備を集約し、上部に蓋を備え、底部に濾過層を持ち、微生物による排泄物や残餌の分解が行われる。底部には水温調整のための熱交換器とファインバブル発生器を配置し、ファインバブルは溶存酸素の向上と魚類に付着するごみの除去を行う。ガラスドームはアグリガラス(赤外線カットフィルター)を採用し、夏の昇温を抑制する。機械室に水温調整機及び殺菌装置をバックアップとして準備し、飼育環境の適合化を行う。
最大の懸念材料はガラスドーム内の高温化である。これに関してはエアーファン、ドライミスト、低温水の循環での対応を考えているが、枯死などに備え大阪公立大学の植物工場研究センターにバックヤード機能を持たせている。
本システムでの生産物については、大阪の食文化(多様性に富む・うま味出汁文化・健康的な食文化等)の8つのアジェンダを掲げたミライの食と文化ゾーンのデモキッチンにおいて、一部の期間に提供する予定で現在若手シェフたちの協力を得ながらレシピ開発中である。
アクアポニックスの技術は、将来、都市での持続的な人間活動および環境保全を行う物質循環・エネルギー有効利用システムのさらなる効率化に貢献すると考えられる。さらには、研究の進展により宇宙での人の生存環境を創るための閉鎖生態系生命維持システムの一部を担うことが期待される。
(文責 佐々木一恵 鈴木秀男 監修 増田昇)